米国の女流推理作家、ヘレン・マクロイの作品は、日本においては翻訳が少なく、推理小説ファンには、あまり知られていませんでした。
しかし、近年、文庫本が次々に発刊されていて、この良質のミステリーの女流作家の名は少しづつ日本の推理ファンの間でも浸透しつつあるようです。
シャーロック・ホームズから、ヴァン・ダイン、エラリー・クイーンと欧米古典推理になじんできた私も、ヘレン・マクロイを知ったのは実は10年ぐらい前になります。
私が最初に読んだ作品は「殺す者と殺される者」ですが、女流作家らしい、平明で細やかな心理描写とサスペンスに満ちた展開に、ぐいぐいと物語に引き込まれたものです。
小説の冒頭から、2重、3重に綿密に張り巡らされた伏線が、最期に一点に結実して事件の真相が明らかになるストーリーを読み終えると、この上ない爽快な満足感を感じ、ヘレンの次の作品に向かわせます。
もし、まだ作品を読んでいなければ、ミステリーの女王といわれるアガサ・クリスティに匹敵するヘレン・マクロイを是非ともお薦めします。
以下に彼女の略歴と主要な作品について紹介しましょう。
ヘレン・マクロイとは?
ヘレン・マクロイは1904年にニューヨークに生まれました。
父親のウィリアム・マクロイは「ニューヨーク・イブニング・サン」紙の編集長で、同じ名前の母、ヘレンは小説家でした。
ヘレンは両親の才能を受け継いだのか、フランスのソルボンヌ大学を卒業後、パリやロンドンでライターとして新聞や雑誌に美術評論などを書いています。
ですから彼女の作品にはその審美眼を生かした細やかで美しい風景や人物描写が特徴です。
1933年に米国に帰国すると、1938年に処女作「死の舞踏」を発表し、推理小説家としてデビューします。
アメリカの本格推理小説の黄金期を代表するヴァン・ダインのデビュー作「ベンスン殺人事件」の出版が1926年、もう一人の巨匠エラリー・クイーンが「ローマ帽子の謎」でデビューしたのが1929年ですから両巨匠に遅れること約10年後に、アメリカ推理界に登場したことになります
代表作は、「暗い鏡の中に」(1950年)と「幽霊の2/3」(1956年)、「殺す者と殺される者」(1957年)などで、1980年の最終作「読後焼却のこと」まで29の長編と多数の短編を書いています。
作風は本格物からサスペンスと幅広く、ヘレン・マクロイの初期から中期の作品は重厚な本格推理にふさわしく、一作一作に工夫が仕掛けられたミステリーで、やがてサスペンス色が強くなっていきますが、女性作家らしく平易で丁寧な描写は読者の共感が得やすい文体です。
短編の名手とも言われ、短編集「歌うダイアモンド」1965年出版はエラリー・クイーンによる歴史的名作短編集「クイーンの定員」に選ばれました。
ヘレン・マクロイの長編の13作品に登場する探偵役は精神科医師のベイジル・ウィリング博士で、ボルチモア出身で第一次大戦に従軍、ジョンズ・ホプキンズ大学で医学を学び、ニューヨークで開業、地方検事局顧問として事件に関わるという設定です。
ベイジル・ウィリング博士は、アメリカ推理小説で(おそらく世界の推理小説でも)、最初に登場する精神科医で、精神医学の専門知識を縦横に駆使し、犯罪者の深層心理を分析し解決していきます。
ヘレン・マクロイは、私生活では1946年、作家のブレット・ハリディと結婚、娘を儲けるものの、1961年離婚します。
1950年にはアメリカ探偵作家協会(MWA)の会長に女性として初めて選ばれ、1953年にはMWA評論賞、1990年には同協会からグランド・マスター巨匠賞を授与されましたが、1994年90歳で死去しました。
本国のアメリカ推理界はヴァン・ダイン、エラリー・クイーンらが全盛期を過ぎると、サスペンスやハードボイルドのミステリーが中心となり、本格派は廃れていきます。
その潮流の中で、日本にも、代表作である「暗い鏡の中に」(1950年)と「幽霊の2/3」(1956年)、「殺す者と殺される者」(1957年)だけが50年以上前に紹介されますが、後は続かず、この3作品も絶版になり、ヘレン・マクロイは長く日本の推理ファンには知られませんでした。
しかし、1982年に最期の作品となった「読後焼却のこと」が日本国内で刊行され、21世紀になって、やっと他の長編作品が紹介され始めました。
現在、全長編作品が翻訳されたことで、ヘレン・マクロイの名は徐々に浸透し人気も高まって来ていると言えます。
次にヘレンの必読作品を紹介しましょう。
「暗い鏡の中に」はヘレン・マクロイの代表作の一つで、オカルト色の強い傑作推理です。ブレアトン女子学院に勤める新人教師フォスティーナ・クレイルは校長から突然解雇を告げられますが、彼女には納得のいく理由は思い当たらず、校長も口を濁し、すぐに出て行くようにと言うだけでした。
しかし、クレイルは思い返すと、着任後周囲の人々が自分を避けていたことに気がつきます。
唯一クレイルと仲が良かった同僚教師ギゼラは解雇に憤慨し、婚約者である精神科医師ベイジル・ウィリングに調査を依頼すると、クレイルの周りでは不気味で怪奇な現象が頻発していたことが判明します。
そして、ついに学園で殺人事件が起こり、学校を去っていたクレイルにも魔の手が襲います。
トリックとしては、現代では珍しいものではないかも知れませんが、全寮制の女子校の美しい風景と相反する闇に潜む邪悪な影が織りなすサスペンスに読者は先へ先へとページを捲らざるを得ません。
最期に犯人が登場するシーンは不気味な雰囲気が漂い、ヘレンはあえてその結末を読者に余韻を残こしたままにします。
「殺す者と殺される者」は、ヘレン・マクロイの小説の中で私が一番好きな作品です。
26歳の大学教師のヘンリー・ディーンは、叔父の遺産を相続するという幸運に恵まれ、仕事をやめ故郷に帰りますが、そこでかつての恋人で今は他人と結婚したシーリアと再会します。
ヘンリーはシーリアへの思いを断ちがたいのですが、シーリアが夫や子供を愛し幸せに暮らしていることを知り、心は傷つきながらもせめて友達として付き合っていきたいと望みます。
しかしその頃から付近に怪しい人物が徘徊し、ヘンリーの運転免許が盗まれたり、小切手が勝手に使われたりと不穏な事件が起こり始めるのです。
そしてシーリアの夫サイモンが出張に出かけた夜、惨劇は起こりました。
冒頭から散りばめられた多くの伏線が結集し、やがて思いもよらない事実がヘンリーの前に姿を現わします。
驚くべき事件の真相が明らかになると、ヘンリーは自分の手で事件の決着を図ろうとしますが・・。
読者は最終章で知るシーリアの心情になんとも言えない悲しみを感じるのではないでしょうか。
当時の最新の精神医学の知識を駆使した先駆的作品で、ヘレン・マクロイの持ち味が十分に発揮されていて必読の作品と言って良いでしょう。
「ひとりで歩く女」は小説の前半を「わたし」の手記、後半を手紙形式でストーリーの大部分が構成された、ヘレン・マクロイらしい技巧を凝らした本格推理小説です。
「誰かがわたしを殺そうとしています」という不穏な文章から始まる手記により物語は進行していきます。
「わたし」は、西インド諸島にある富豪のいとこ、ルパートの別荘でバカンスを過ごし、ニューヨークへ帰るため乗船しますが、ルパートから預かった封筒から出てきたのは10万ドルの札束でした。
「わたし」は驚愕するとともに、同船する曰くありげな人物たちがこの大金を狙って襲ってくるのではないかと怯えます。
やがてルパートの死亡のニュースが伝えられ、船内では毒蛇が野放しになるという騒動が起こり、「わたし」は身の危険を一層感じ、手記の執筆を急ぎますが、突然手記は中断され、乗客の女性の死体が発見されます。
後半では「わたし」が警察署長あてに書いた手紙によりストーリーが展開し、ついに事件の首謀者が姿を現わし、「わたし」は絶体絶命の危機に陥るのですが・・・。
綿密に張り巡らされた伏線、次々に起こる事件は読者を飽きさせず、読み終えればすべてがジグゾーパズルのように整合していきます。
折原一の小説を思わせるスト-リー構成ですが、1948年の作品にもかかわらず、現代でも通用する斬新でサスペンス感あふれる作品です。
人気作家とそのエージェント、出版社社長ら夫婦がパーティーを開き、「幽霊の2/3」というゲームに興じる最中に、作家エイモスが毒殺されます。数合わせでパーティーに招待されていた精神科医ベイジルは、事件の真相を解明するべく精力的に調査に着手しますが、被害者である作家こそが正体不明の謎の人物であることが明らかになっていきます。
パーティーでの殺人という本格推理の典型的な設定ですが、ヘレン・マクロイは登場人物とその複雑な人間関係を綿密に描き、読者を事件の謎に引き込んでいきます。
そして、最期に用意されていたのは、ヘレンならではの驚くべき真相でした。
読者は、読み終えると小説の題名である「幽霊の2/3」までがその真相の伏線だったことがわかります。
ヘレン・マクロイの作品としては早くに日本に紹介されたものの長く絶版になっていて、推理ファンには幻の名作とされていました。
”医師も注目”ヒト幹細胞エクソソーム化粧品【Lejeu(ルジュ)】![]()





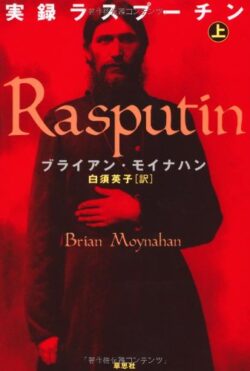

コメント