大河ドラマ「麒麟が来る」が好評のうちに終わりました(2020年12月)。
過去の大河でも織田信長は何回も登場していますが今回は信長の珍しいシーンを見ることができました。
信長が時の正親町天皇に強要して天皇家に古来より伝わる香木の「蘭奢待(らんじゃたい)」を切り取る場面のことですが、この歴史的な事件が映像で描かれたのは初めてではないでしょうか。
この出来事は、蘭奢待が時の権力者を争わせるような類い希な宝物であったことを示した事件でもありました。
また蘭奢待に代表される香木、そして香木が発する芳香を楽しむという文化や芸道としての「香道」が公家社会だけでなく武士社会にも広がっていたことも意味しました。
香道とは、香りを鑑賞する芸道で華道、茶道とともに日本の三大芸道の一つです。
花を飾るとかお茶を飲むというという習慣は世界各国に見られますが、香りを楽しむという香道は日本独自の文化といって良いでしょう。
このような香りの文化、そして香道はどのように生まれたのでしょうか?
蘭奢待とはどういうもので、信長は何のために強引に蘭奢待を切り取ったのでしょうか?
香木の到来と香り文化の始まり
香道が確立したのは室町時代ですが、香を楽しむという文化は香木が我が国へ伝来した時を以てその始まりとしています。
日本書紀には、595年(推古天皇3年)4月に淡路島に一囲(いちい/約1.5m)ほどの沈水(じみ)が漂着したと書かれています。
沈水とは沈水香木のことで、香りの成分である樹脂が長い年月をかけて原木に沈着したものです。
その沈着した部分を沈香(じんこう)といい、比重が水より重く水に沈むことからそのように呼びました。
島人が沈水とは知らずに薪(まき)としてかまどで焚いたところその芳香の素晴らしさに驚いて朝廷に献上したといいます。
沈水の原木は、ベトナム・カンボジア・マレー半島・インドネシアなど東南アジアに分布するジンチョウゲ科の樹木で遠路はるばる海流に運ばれて淡路島に到達したのでしょう。
沈水が流れ着いたといわれる淡路の江井の浦(現淡路市江井地区)には枯木(かれき)神社がありご神体として流木を祀っています。
また現在、淡路島は全国トップの線香生産地となっています。
仏教による香り文化の普及
その後、754年(天平勝宝8年)、苦難の末に来日した唐の鑑真和上は、正当な戒律とともに、仏教儀式に必要な多数の香木・香料をもたらし、それらを調合して蜜で練り上げる合香の製法を伝えました。
当時、香は供香(ぐこう)といい、清浄な香りにより、仏事を荘厳に演出することが目的として使われました。
宗教空間に漂う香の香りは心の浄化作用により人々に功徳を感じさせたのです。
こうして我が国では仏教とともに香の文化が広がっていきます。
平安時代になると、貴族の間で香を衣服、頭髪、部屋などに立ち籠める「空薫物(そらだきもの)」の風習が生まれ楽しむようになります。

薫物は今の練香と同じもので香木を粉末にし梅肉や蜂蜜を混ぜ練り固めた公家好みの優美な雰囲気を持つ薫物で、その薫物を鑑賞し、技術や香りの優劣を競う「薫物合(たきものあわせ)」という雅やかな遊びもさかんに行われるようになります。
2大流派による香道の完成
鎌倉時代に入り、武士の社会でも香の魅力は人々を惹きつけますが、社会の中心となった武士は落ち着いた清爽な香りの沈水香が好みました。
当時、南宋貿易が盛んになり多量に上質の香木が入手しやすくなったことで、公家や有力武士は競って香木を集めます。
室町幕府に入ると、足利義政を中心とした東山文化の中で一定の作法のもとに香をたしなむ香道が完成します。
その創始者といわれているのが、公家では宮中の御香所役をつとめた三條西實隆(さんじょうにしさねたか)で、武家では義政のそばで同朋衆として仕えた志野宗信(しのそうしん)でした。
三條西實隆の流派を「御家(おいえ)流」、志野宗信の流派を「志野(しの)流」と呼び、現在でも香道の2大流派として続いています。
このような背景の中で、「蘭奢待」は時の権力者にとって垂涎の名香木として位置づけられていました。
天下の香木・蘭奢待とは?
蘭奢待は、一説では733年(天平5年)に中国経由で渡来し、聖武天皇に献上されたといわれ、伽羅(きゃら)という種類の天下一品の香木です。

全長156cm、最大径43cm、重量11.6kmのほぼ錐形をしています。
正式名称は「黄熟香(おうじゅくこう)といい、蘭奢待という名は雅称(風雅な呼び方)ですが、蘭奢待という文字には、光明皇后により奉納された「東大寺」の文字が隠されています。
蘭奢待は長く聖武天皇の遺愛物を収めている正倉院中倉に保管されてきましたが、平安末期、源頼政が鵺(ぬえ)と呼ばれる妖怪を退散した功により近衛天皇からその一部を賜ったという伝説があります。
室町時代には3代足利将軍義満が切り取り、6代義教、8代義政も2寸を截香(せっこう:香木を切ること)したとされ、時代が下がって明治10年、明治天皇も2寸を切り取り、その跡にはそれぞれ付箋が残されています。
近年の調査では過去50回程度切り取られているとみられています。
信長の截香と正親町天皇の不快感
信長が蘭奢待を切り取った事件は「信長公記」に記されています。
1574年(天正2年)3月12日、信長は上洛し正親町天皇に蘭奢待の所望の奏聞をおこなうと、10日後に御院宣が出て許されます。
3月28日、信長は松永久秀より摂取した奈良の多聞城に到着、東大寺に使者を立て正倉院を開かせ、長さ6尺の長持に収まったこの名香を多聞城に持ち帰らせます。
信長は蘭奢待を城内に作った舞台の上に置いて見聞し、部下たちにも「末代の物語」にするために拝見するよう命じます。
そののち、足利義政以来、歴代の将軍が所望しても許されなかった蘭奢待を定法通りに約1寸(3cm)四方に2個切り取りました。
信長公記は「本朝において御名誉、御面目の次第、何事かこれにしかん」と書いています。
信長はその1個を慣例通り天皇に献上し、1個を自分のものとしました。
信長は蘭奢待とともに「全浅香(ぜんせんこう)」(紅塵)という香木も正倉院より取り寄せていましたが、これは見るだけにとどめています。
信長はその後、自身で正倉院に入り内部を見聞しています。
このように信長は、蘭奢待の外部への持ち出しとその截香、さらに天皇の倉へ入るという前例のない行動を行ったのです。
正親町天皇は信長の金銭上の支援や内裏修理などの功績により蘭奢待截香をやむなく認めました。
しかし、所望の奏聞の前に天皇を差し置いて信長寄りの公家、二条晴良らで蘭奢待截香を進めようとしていた経緯や、許しを得た後の性急な截香など信長の振る舞いに強い不快感を持ちます。
そこで正親町天皇はその不快感を示すために、献上された蘭奢待を信長と敵対している毛利輝元に与えました。
毛利輝元は拝領した蘭奢待を長く手元に置くことなくすぐに厳島神社に奉納しますが、輝元はこの蘭奢待の截香された経緯を知って災いを避けるために神社に奉納したものと思われます。
また正親町天皇は九条稙通にも書状とともに蘭奢待の1片を授けていますが、その書状では信長の截香が不意に行われたことに触れていて自身の気持ちを表したかったのでしょう。
香り文化と蘭奢待、信長の截香とは?・まとめ
信長の蘭奢待を切り取るという挙に出た一つの理由は、自分が天下人となったという証を公家や武士社会に示すためでした。
蘭奢待を切り取った足利義満を始めとする歴代の将軍と並ぶ実力者であることを誇示するために行ったのです。
それだけでなく、信長は功を上げた武将を茶会に招き、高価な茶器を与え服従させていくという「御茶湯御政道」を推進し芸道を利用した統治を行いましたが、その茶会で香りという舞台装置の役割を担っていたのが香木でした。
信長が蘭奢待に執着したのは、天下に名だたるこの香木を活用することで「御茶湯御政道」をさらに強化するためでもあったのです。

実際に千利休の茶会で蘭奢待を焚いた記録が残っていて、信長より授けられた蘭奢待の可能性が高いと思われます。
しかし、正親町天皇の信長への不快感が、やがて公家・武士社会の一部にあった反信長の感情をさらに醸成することになったとすれば、明智光秀の謀反の遠因になったとも言え、信長の蘭奢待截香は自身の意図とは反対の結果を招いたことになります。
さて、信長の後、蘭奢待を截香したのは明治天皇だけです。
1877年(明治10年)、2月9日、明治天皇は奈良に行幸し正倉院を見聞した際、蘭奢待を截香します。
長さ2寸を切り取り、東大寺で小片にして焚き、「薫烟芳芬(くんえんほうぶん)として行宮に満ちた」と記録されています。
信長以来、303年ぶりの蘭奢待の截香でした。
明治天皇は1879年(明治12年)6月にも蘭奢待を截香させていて、これが歴史上最期の截香となりました。
参考:香道の歴史/本間洋子、香と日本文化/太田清史


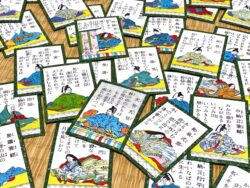

コメント